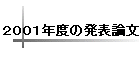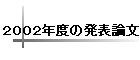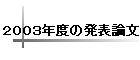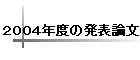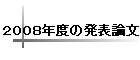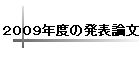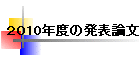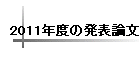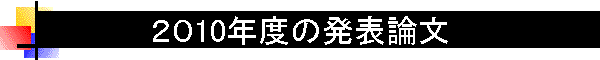 |
|
コア・コンピタンスについて考える
古武術の型を紐解いて分かること
野 川 栄 一
コア・コンピタンス(core competence)とは、私にとって、言葉の響きから可能性を感じる言葉となりました。辞書の解説では、「『
コア・コンピタンス経営 − 一大競争時代を勝ち抜く戦略』ゲイリー・ハメル、C・K・プラハラード著、一条和生訳
、日本経済新聞社
1995年(『Competing
For The Future』の邦訳)」から一般に認知されたもので、「顧客に対して価値提供する企業内部の一連のスキルや技術の中で、他社がまねできない、その企業ならではの力のこと。競合他社に対しては、経営戦略上の根源的競争力につながるものであり、他社との連携などの際に相手に与える影響力や業界イニシアティブの強弱のキーともなる」(IT情報マネジメント辞書)というものです。
最近、私は実践している古武術の型について、“再発見した”という自覚を持ちました。型は型であり、実践性又は実戦性における身体の“練り”を醸成させるためのツールであると捉え、当然に、型に内在される動き本来のあるべき動きを集約した“生きる型”との認識は持ち合わせていました。しかし、これは観念の世界での認識であったようで、頭をガツンと打ち鳴らされる事態が思いもよらぬ瞬間にふっと湧き出たのです。この衝撃は、“型から型の恵みをいただけた”という一瞬の出来事でした。直面した一瞬の貴重な体験をコア・コンピタンスの視点から紐解くことで、型に内包されたノウハウなど、型の存在意義を顕在化させてみたいと思います。この試みを軸に、各分野において存在するコア・コンピタンスの検証を紐解いてみたいと思います。
古武術の稽古において、型として残されている一つ一つの技を、技の組立てを順次行うことで、一つの技の稽古が完成します。この技の流れを反復稽古することで上達が約束されます。この約束を前提として、稽古をする者は皆、稽古をすることを止めない限りにおいて技は上達するというテーゼを打ち立てます。次に、テーゼについて検証を試みます。条件を平面つまり見た目の上達として考察すると、上達と稽古量とは比例しています。一般的にみてもこの比例関係は正しいといえるでしょう。では、考察条件を立体、つまり、見た目だけではなく有効に極まる技という視点で捉えてみると、この考察は通常の稽古では検証できないという事態に陥ってしまいます。なぜならば、古武術は試合をしません、そして、生き残りの術を長年の修行を積んで獲得することが主眼であることから、本物の技も見せないのです。この立体的考察は、“不心得者”という烙印がともすると押されてしまいます。“秘伝の技”という技への賞賛が錯覚の世界へと人々を落し込み、“形だけ”の技に、“これが古武術の技であり歴史を積み重ねた技は凄い”という言動を許してしまうのです。“実際の技は”という疑問に対して、的確な答えや筋道が導き出せない武術家は多々存在すると思われます。
型稽古とは、「型を型どおり実行することで技を獲得し、その獲得した技の稽古を実践することで技の深みを知り、深みという錯覚を通して型を理解し、自分に型をはめ込むことで理解を深める稽古である」と定義します。この技の展開を自由自在に行使することが、次なる技の深みを作ります。従って、稽古を継続している限りにおいては、永遠に技の深みを探求する旅に終わりはありません。このように観念的な連続する技の構築システムは理解できますが、システムではない人間感からはどうなのだろうとの疑問が湧き起こるのです。次に、稽古をした技は、極まる技か、極まらない技か、有効な技か、有効ではない技かなどと自分自身の今の立場で技の熟成度を測る心的欲求が支配します。この欲求から、型の成熟度や浸透度などをコア・コンピタンスの視点から探ってみたいと思います。
型の自身への認知度を意識することで、技の熟成度の比較が可能となります。技は一対一の掛け合いで伝授されます。その光景を他の修行者は見ることで、自分の技との対比を通して技の向上を意識化に置くことができます。ここでの意識は普遍性ではなく、あくまでも個人レベルでの意識化です。
古武術に接して30年程になります。柔術系の技は150を超える数を有していることから、技に対する得手・不得手、好き・嫌い、派手・地味等の感情が交錯し、その感情が技の向上に多々影響を与えます。修行当初から、苦手といえる技があります。型を型どおりに稽古し、型の本質を分析し理解することで技の奥にある型を身体に刻んできました。すっきりした形で型に結びつかない技に対しても同じ工程で技を身体に刻む稽古を積みました。しかし、しっくり来ない技は存在し解決できずにいました。最近、“ふっとした”ところから、何回、何百回、何万回と数知れない稽古を重ねてもしっくり来なかった技が、型どおりにすっきりと稽古ができたという実感がありました。これは、型の認識を根本から否定したところから発見したもので、力の強弱で型を技にしていたものを技の途中で力を絶ち、型を組立て直した結果技の駆動が“すっきり”したのです。型を型どおりに稽古したことで、型に内包されていたノウハウを我が手に掴んだ一瞬、この一瞬を私は型の恵みをいただけた一瞬と捉えました。
型を型どおりに稽古することは技の築きであり、築いた技を“すっきり”する形で自分の身体に深く刻み付けたことで、技の奥義の気づきができたと考えます。多くの者が同じ土俵の中で稽古をしていますが、同じ感情で技を型どおりに稽古できたと思うものは一人として存在しないことでしょう。技は個人的な世界観に包まれ、技に対する感情も個々の判断で差別化されるからです。しかし、型は個人レベルのものではありません。型の汎用性は重要で、型があるから技となり、技の検証は型を通してのみ行われます。柔術系の技は150を超える数を有しています。技の展開は無限に拡大していくことでしょう。しかし、型は150程であり、無限に拡大する存在には成り得ません。型の理解は、個人の理解レベルで無限に拡大する可能性はありますが、絶対的、超越的に君臨する型は一つの技に対して一つしか存在しません。この型の存在は、古武術の流派にとってコア・コンピタンスであり、コア・コンピタンスの存在そのものを意識した瞬間に、流派の歴史的文化的価値が姿を現すものであると考えます。各分野に存在するコア・コンピタンスは、言葉やスキルでその存在が示されるなど顕在化しています。しかし、心的な理解は、個人レベルでは無限に拡大しすぎ、各分野の根幹にとって強力な武器には成り得ていないように思われます。各分野において、真のコア・コンピタンスの理解は、組織化された団体が、団体の存続を賭けた危機的状況下において、このコア・コンピタンスから生存権を勝ち取ろうとする強い意思を打ち出したとき、本物の理解を得ることとなるでしょう。通常、団体の生存は当たり前という個人の集合体では、危機的状況はほとんど体験できていません。しかし、会社組織においては、会社の存続には問題はないが、利益率が激減したなどの状況は多々あることでしょう。このような場合に、自社のもつコア・コンピタンスを再度検証し、コア・コンピタンスに内包された新たなノウハウを発見できた場合には、旧コア・コンピタンスの理解に新コア・コンピタンスの理解を重ね、融合、転換、展開、否定、肯定を繰り返すことで、全く新しいコア・コンピタンスの構築を成し遂げられるでしょう。成功した暁には無限の発展が約束されることでしょう。そして、築きから気づき、気づきから築くことで、コア・コンピタンスを永遠に信頼し利用できるサイクルが構築され、サイクルとして駆動し続けるのです。
じっせん第19号で、「過信という誤信を防止する心得について−
慶長通宝から考える」において9つの心得を掲出しました。この心得をコア・コンピタンスの概念に当てはめると、共通する部分が多々あります。心得の7番目に、「経験は検証の幅を広げる:キャリヤ蓄積から身体進化を論ずると、“経験を積む”とは、理屈を言うためのものではなく検証の幅を広げるためのものとなる。現在の自分と過去の自分との会話は技を介して行い、今の自分と未来の自分との会話も技を介して繋ぐのである。」から、コア・コンピタンス風に心得を考えてみたいと思います。これは、技の獲得に対して、初心者のころの感情と時を過ぎ上級者になったときの感情は、技を介したときには同等であり“経験を積む”ことによって、技つまり型の検証を繊細に分析し、更なる進化を遂げる未来の技の獲得を図ることを意味しています。型そのものがコア・コンピタンスであり、その型の研究は一生涯続けなければ本物の成果を得ることはできません。従って、生涯現役が必然で、大きな意味を持つという心得になっています。
テレビ番組で、ある社長に触れる機会がありました。社長の心得として幾つか紹介があり、�ハイテク&匠の技、�特化した品物づくり、�give
& given、�発想(何々したい)、�生涯物づくり、などでした。また、この企業の製品は物まねされるが製品の質で撃破しているとのことで、それぞれの部品組立工程に匠の工員が存在していました。0.02ミリメートルの厚さも匠の指感覚で克服し対応する場面が放映されたのです。工員は何百箇所ある作業工程における特定箇所を、何十年という歳月を費やし、匠の技を熟成させたのでしょう。この企業の匠養成法は、全体の組立作業のある一部門を専門化させるもので、匠の社外流失を抑え、留まる匠に対しては、匠としての名声が社内に満ち溢れ、匠を留まらせるに充分な匠としての自覚が、匠の技に拍車を掛け、更に年月を重ねることで匠の技は匠の技と成り得ます。この仕組みは正にコア・コンピタンスであろうと思いました。
古武術の型を紐解く方法で、個人用のコア・コンピタンスの活用法を模索します。まず、自社のコア・コンピタンスについての優位性を学習します。次に、学習の成果として、コア・コンピタンスの優位性を認識します。この認識は、コア・コンピタンスのノウハウの部分とそれ以外の効用の部分の二つであると仮定します。それ以外の効用の部分の意味するものは、自社のコア・コンピタンスの形から他社のコア・コンピタンスを相似形で描き、描いた相似形を分析することで得られた成果とします。相似形は他社のコア・コンピタンスそのものではありません。しかし、自社のコア・コンピタンスと他社のコア・コンピタンスとの違いを、自社のコア・コンピタンスとの対比を通し、自社のコア・コンピタンスの発展に結びつく可能性を秘めています。異分子を取り入れることは難しい問題ではありますが、異分子を取り入れなければ自社のコア・コンピタンスの活力ある発展は望めません。自社のコア・コンピタンスを同質のまま繰り返していくと、やがて自社のコア・コンピタンスは退化すると思うからです。異分子を異分子で取り入れる危険を避けるためには異分子を相似形で現し、その分析の成果を自社のコア・コンピタンスの欠けている部分に補うという認識で認知することで、自社のコア・コンピタンスの理解を深くすることができると考えます。基本は、自社のコア・コンピタンスです。実は、この思考の展開法は、古武術における型を理解するための方法であり、型を実践的に又は実戦的に理解するにはこの方法しかないと私は考えております。
30年程継続して稽古している古武術において、“頭をガツンと打ち鳴らされる事態が思いもよらぬ瞬間にふっと湧き出した”ことから型について、コア・コンピタンスの視点で検証しました。型における“再発見した”という自覚は、型が型として存在する中で、型にコア・コンピタンスが内在され、この内在から実践性又は実戦性における身体の“練り”を醸成させるとの意識です。ツールとしての型は、当然に、型に内在される動き本来のあるべき動きを集約した“生きる型”であり、この型はコア・コンピタンスとしての型でもあったと実感したのです。型とコア・コンピタンスの関係の理解は、今後の武術修行及び武術指導にとって大変意義あるものとなりました。
さて、結局のところ、「顧客に特定の利益をもたらす一連のスキルや技術を言う。」がコア・コンピタンス(core
competence)であり、企業は、�顧客への利益とは・・・云々、�そのためのコア・コンピタンスとは・・・云々、を顕在化させることを長年に亘って継続することで、企業の「強み」を生み出すことでしょう。そして、他社との差別化を図ることで、自社を有利に導くコア・コンピタンスを確立させるのです。従って、観念的なコア・コンピタンスの理解ではない実践的な理解が個人レベルの理解にまで浸透したとき、コア・コンピタンスは企業の全社員を対象とした魅力ある企業風土を醸成させることでしょう。
また、型を通した技の理解は、型という絶対的な存在を前提に成り立つものです。つまり、本物の型の存在が自分の前にあることを意味します。この環境は自然の成り行きで到達したものもあれば、自分で引き寄せた場合もあります。しかし、型を主眼においたコア・コンピタンスの理解には多くの歳月を費やすことから、コア・コンピタンスとしての型の存在の有無の検証は、己の意識化・無意識化を問わず短期間での検証はできません。長期の検証が必然化される型における検証では、検証する個人の存在を認める型が本物の型であって、歴史的構築から外れた型である個人が構築した型では時代に耐え得るコア・コンピタンスには成り得ないと考えます。本物の型や未来に希望を繋ぐ型に巡り会う又は会ったという実感は、偶然の出会いの賜物で、実は、この実感を得ることが、コア・コンピタンスの本質ではないかと考えております。
参考文献
【コア・コンピタンス経営−未来への競争戦略、ゲイリー・ハメル&C・Kプラハード著、一條和生訳、日本経済新聞出版社、2001年1月5日第1冊発行】
【過信という誤信を防止する心得について− 慶長通宝から考える 野川栄一
じっせん第19号2009VOL
10-No.1】 |
|
|
|
Web designed by The Jissen juku
このウェブについての質問およびコメントのある方は |